個人型確定拠出年金(iDeCo)とは?節税のしくみや加入資格まとめ

確定拠出年金 は、その名の通り「掛金を拠出して自分の年金とする」制度です。とくに税制面での優遇があり、老後の資産形成の手段としては最強とも呼ばれています。
制度には2つの種類があり、企業が掛金を拠出する「企業型確定拠出年金」と、個人が掛金を拠出する「個人型確定拠出年金」があります。
このうちの個人型確定拠出年金は「iDeCo(イデコ)」という愛称で親しまれ、多くの人が老後の資産形成のために利用しています。
iDeCoの利用は何歳から?どんな人が運用できる?
まずは、個人型確定拠出年金(以下iDeCo)を利用できる人を確認しておきましょう。
| 国民年金区分 | 具体的な職業・他の制度の加入状況 | 月額限度額 | |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業者・フリーランスなど (20歳以上60歳未満) |
6.8万円 (年額81.6万円) |
|
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員など (20歳以上65歳未満) |
企業年金に加入していない | 2.3万円 (年額27.6万円) |
| 企業年金に加入している | 2.0万円(※) (年額24万円) |
||
| 第3号被保険者 | 専業主婦(夫)など (20歳以上60歳未満) |
2.3万円 (年額27.6万円) |
|
※企業年金などに加入している人のiDeCo拠出限度額は「上限2万円」となります(=月額55,000円 -各月の企業型DC・DBなどの掛金額)。
上記のように、iDeCoは基本的に20歳以上60歳未満であれば加入・利用ができます。
その中でも国民年金区分の第2号被保険者=会社員・公務員にあたる人で、60歳以降も会社員や公務員として働き、厚生年金に加入する場合は、65歳まで加入が可能です。
ただし、会社員・公務員の場合「企業型確定拠出年金(企業型DC)」や「確定給付企業年金(DB)」などを利用している人については、掛金の上限額が変わることも覚えておきましょう。
またiDeCoは作られて間もない制度であることもあり、改正が度々入ります。2024年は拠出限度額の変更があり、第2号被保険者が企業型DC・DBなどの他制度に加入している人でiDeCoを併用する場合の拠出限度額が「1.2万円 → 2万円」に引き上げられました。
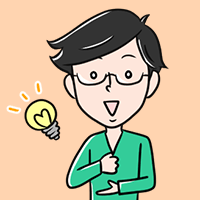 ひっきー
ひっきー
iDeCoで投資できる3つの商品
さて次は「iDeCoで投資できる金融商品」についてみていきましょう。iDeCoで投資ができるのは下記の3つの商品に限られます。
- 定期預金(元本確保型)
- 保険(元本確保型)
- 投資信託(元本変動型)
上記をみてわかる通り、実はiDeCoでは株式投資ができません。優待投資家にとっては痛いところですが、別物と割り切ってiDeCoの利用を考えていきましょう。
さて上記の3つの商品で何に投資するかですが、拠出する金額内であれば商品の組み合わせは自由となります。 つまり「投資信託 + 定期預金」でも「定期預金 + 保険」でも「投資信託のみ」でも問題ありません。
iDeCoの投資商品の特徴・注意点
特徴・注意点①:「元本確保型」の投資商品について
定期預金・保険などの元本確保型については、運用をしても運用益はほぼ出ないことを覚えておきましょう。仮にインフレ(物価の上昇)が起こると実質的に価値が下がってしまいます。
とくに保険については、途中で解約してしまうと「解約控除」という費用がかかってしまうため、結果として元本割れの可能性も高まります。
元本確保型という名前とは裏腹に、このようなデメリットがあることを知っておきましょう。
特徴・注意点②:「元本変動型」の投資商品について
元本変動型の投資信託は、運用がうまくいかなければ元本割れの可能性もあることは否定できませんが、反対に運用がうまくいけば老後資産が増えることになります。
一長一短の商品の性質をきちんと理解し、理想とする老後資金と、自分がどれだけのリスクを取れるのかという点をおさえて商品を決める必要があります。
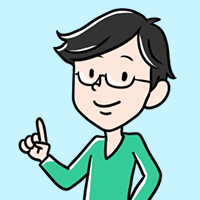 ひっきー
ひっきー
運用が順調にいくと、後ほど説明する「複利効果」をフルに活用できるので、効率的な資産形成につながります。
iDeCoを利用する3つのメリット
冒頭でiDeCoを利用することによって「税制面の優遇がある」とお伝えしましたが、そのほかにもiDeCoを利用するメリットがたくさんあるので、具体的に解説していきます!
メリット1:掛金(積立金)は全額所得控除となる
iDeCoでは毎月一定額の掛金を拠出しますが、この掛金が全額所得控除となります。
たとえば、課税所得400万円の会社員が月額23,000円を積み立てた場合、約84,000円の節税効果が期待できることになります。
所得控除=課税所得が少なくなるので、所得に応じて税額の変わる「所得税」や「住民税」が安くなる=税制優遇があるということです。
 ひっきー
ひっきー
メリット2:複利の効果が得られやすくなる
複利とは
複利とは「当初の元本+その元本で得た利益」を足して再投資し、新たに利益を生ませることです。
利益が利益をよぶことで、とくに長期運用する投資で効果を発揮します。
その一方で「単利」という言葉もあります。こちらは当初の元本金額のままで運用していく方法を指します。
通常口座での投資だと、利益確定し現金にするタイミングで運用益・分配金に対して約20%の課税がされるため、再投資する場合に複利効果が小さくなってしまいます。
しかしiDeCoを利用すると「運用益・分配金は非課税であること + 自動的に再投資に回される」ので複利効果を得られやすくなるのです。
ただし、運用が終わった後の受け取り時には課税される場合があるので、その点はご注意ください。
メリット3:投資信託の運用にかかるコストが割安
投資信託の運用には下のような3つのコストがかかります。
- 購入時手数料(販売手数料)
- 信託財産留保額
- 運用管理費用(信託報酬)
こうした投資信託で通常かかるコストが、iDeCoを利用すると割安になります。(1)と(2)の費用については、ほとんどの商品でかからないですし、(3)についても下記の表のように割安となります。
| 国内株式型 | 国内債券型 | 外国株式型 | |
|---|---|---|---|
| iDeCo向け | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
| 一般向け | 0.8% | 0.4% | 0.9% |
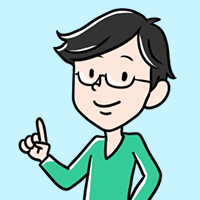 ひっきー
ひっきー
ただし、加入時手数料(税込2,829円)や、毎月発生する口座管理手数料(約240円~)など、iDeCoのみでかかる費用もあります。しかし、それを含めてもiDeCoを利用した投資信託の運用コストは割安といえます。
iDeCoを利用するうえでの2つのデメリット
iDeCoのメリットがわかったところで、こんどはデメリットについても見てみましょう。
デメリット1:60歳になるまで引き出せない
iDeCoでは、拠出した掛金や運用益について気軽に引き出すことはできません。加入期間によって受給開始の年齢が変わり、最短でも60歳を超えなければ引き出せません。
下記に引き出しが可能となる年齢をまとめたので参考にしてください。
| 確定拠出年金の加入期間 | 受給開始年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳~70歳 |
| 8年以上 | 61歳~70歳 |
| 6年以上 | 62歳~70歳 |
| 4年以上 | 63歳~70歳 |
| 2年以上 | 64歳~70歳 |
| 1か月以上 | 65歳~70歳 |
デメリット2:元本割れの可能性がある
投資信託などに投資をする場合、大きなリターンも見込めますが、その逆に元本割れのリスクも当然あります。
しかし、長期間運用での複利効果で元本が増えやすくなるというのは間違いなく、さらに税制上でメリットの多いiDeCoを活用することは資産形成の手段として悪手ではありません。
iDeCoを利用するには~金融機関の選び方~
iDeCoのメリット・デメリットはご理解いただけたでしょうか。少なくとも老後資金を構築するための手段として、強力な制度であることはお分かりいただけたかと思います。
さて、最後にiDeCoを利用する流れを確認しておきましょう。
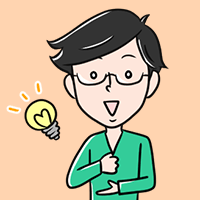 ひっきー
ひっきー
- iDeCoを利用する金融機関を選ぶ
- 自分の投資する金融商品を選ぶ
- 掛金を拠出して運用する
この中でとくに大切なのは①の金融機関の選び方です。なぜかというと、投資商品・手数料が金融機関によって違うためです。
また、金融機関を一度決めたら変更するのが大変ですし、その際に手数料を取られることもあるので慎重に決めたい部分なのです。
iDeCoをはじめるなら「ネット証券」がおすすめ
iDeCoが利用できる金融機関は、主に下記の分類に分けられます。
iDeCoが利用できる金融機関
- 証券会社
- 銀行
- 保険会社
まず、おすすめしない金融機関として挙げられるのは「銀行・保険会社」です。なぜかというと「商品の選択肢が少ない」ことや「手数料が高いこと」、「サポート体制の不安がある」などのデメリットがあるためです。
 ひっきー
ひっきー
というわけで、iDeCoにおすすめなのは、ずばり「証券会社」ということになります。とくにネット証券の投資商品ラインナップは豊富ですし、何より自宅で口座開設ができてしまうというところも長所でしょう。
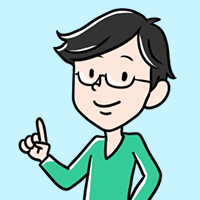
iDeCoをはじめる証券会社 選ぶコツ
iDeCoを始める証券会社を選ぶ際のコツは「提供商品の内容」と「通常投資の考慮」です。
提供商品の内容
iDeCoで投資ができる商品は証券会社ごとに異なります。
楽天証券やSBI証券は、独立系の投資信託にも投資できるところが魅力ですし、マネックス証券は厳選に厳選を重ねた商品ラインナップなので、手間をかけずにいい商品を選べるのが魅力です。
またその逆に、松井証券は業界最多水準の商品ラインナップとなるので、じっくり自分にあったものを選べるという利点があります。
通常投資の考慮
iDeCoの運用と、通常投資をする金融機関は別でも問題ありませんが、同じ証券会社にしておくと「管理がしやすい」というメリットがあります。
通常投資をするのであれば、その証券会社でかかる売買手数料や、投資ツールの使いやすさ、クレカ積立のお得さなども考慮しましょう。
| 証券会社 公式サイト |
投資信託本数 | 特記事項 | 詳細 情報 |
|---|---|---|---|
| 楽天証券 | 36本 | 証券総合口座と共通のログインID・パスワード | 詳細 |
| SBI証券 | 38本 | 加入者数No.1 | 詳細 |
| マネックス証券 | 28本 | 専用ロボアドバイザーが提案 | 詳細 |
| 松井証券 | 40本 業界最多水準 |
充実したサポート体制 | 詳細 |
iDeCoは老後資金を構築するための強力な制度です。60歳まで引き出せない縛りもありますが、税制面で優遇されるので活用しない手はありません。
また、長期間の運用が前提となること + 運用益が非課税となることで複利効果を最大限に活かせます。また複利効果は運用期間が長くなるほど効果が大きくなるので、なるべく早めに始めましょう。
iDeCoを始める金融機関は、とくに大きな理由がなければ証券会社でよいでしょう。通常投資も始める人は手数料やツールの使いやすさなども考慮してくださいね。
iDeCoについて、さらに詳しく知りたい人はグループサイトである「やさしい投資信託のはじめ方」についても目を通してみてくださいね♪





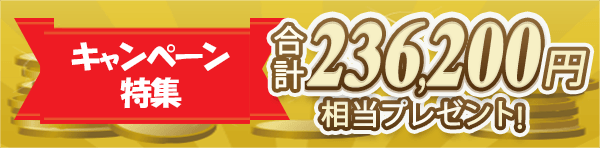
そんな「iDeCo」について、利用するメリットやルールを一挙にまとめてみました!