- TOPページ
- 株主優待の裏ワザ・お得情報
- クロス取引の費用・手数料はどれくらい必要なのか?
クロス取引の費用・手数料はどれくらい必要なのか?

前のページまでにクロス取引の基本や、クロス取引に向く証券会社についてまとめました。最後にクロス取引の費用についてみていきます。
クロス取引の費用は少し複雑
通常の株取引であれば、現物取引の手数料さえ気にしていればいいのですが「現物買い + 信用売り」を利用するクロス取引の費用は下記のように少しだけ複雑です。
クロス取引の主な費用
- 現物買いの手数料
- 信用売りの手数料
- 貸株料
①現物買い、②信用売りについてはイメージしやすいので問題ないと思いますが、クロス取引においては耳慣れない「③貸株料」という費用もかかってきます。
貸株料とは
貸株料とは「信用売りをするときに、証券会社から株を借りるためのお金」のことです。その金額は「約定代金 × 貸株料率(%)÷ 365 × 信用売した株の保有日数」で計算ができます。
SBI証券でクロス取引をした場合の費用例
ここではSBI証券を使って、銘柄Aを権利付き最終日にクロス取引して、権利落ち日に決済した場合のコストを出してみます。
- 「銘柄A」をクロス取引した際の情報
- ・株価 … 900円
- ・取得株数 … 100株
- ・約定代金 … 90,000円(900円 × 100株)
- ・クロス取引をした日 … 権利付き最終日
- ・クロス取引の決済日 … 権利落ち日(権利付き最終日の翌日と仮定)
- ・信用取引の種類 … 一般信用取引(無期限)
まずは「現物買いの手数料」です。SBI証券では、ゼロ革命の対象者である場合、現物・信用取引の手数料が0円となります。
次に貸株料ですが「90,000円(約定代金)× 1.10%(貸株料率)÷ 365 × 2日(信用売した株の保有日数)」という計算で5.4円がかかってきます。
以上を足したものがクロス取引の費用となります。
現物手数料 0円
+
信用売り手数料 0円
+
貸株料 5.4円
=
約6円がクロス取引の費用
もし優待の価値が2,000円あれば、2,000円-約6円=約1,994円ほどが利益となります。
売却手数料はかからない?
「株を買ったんだから売るときにも手数料がかかるんじゃないの?」と思われるかもしれません。実はクロス取引をおこなった場合は品渡し(現渡し)という特殊な取引ができます。
品渡しとは
品渡しとは、売り建てた株を現金で買い戻すのではなく、保有している同じ銘柄・同じ株数の現物株を差し入れて決済する方法です。
クロス取引では、同株数の「売建玉」と「現物株」を持っている状態なので、この品渡しでの決済ができるのです。
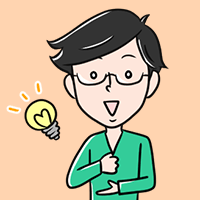 ひっきー
ひっきー
品渡しの手数料は証券会社によって変わりますが、SBI証券の場合は手数料がかかりません。つまり例に出したSBI証券でのクロス取引の場合は、売却手数料がかからないということになります。
費用・手数料をシミュレーターで徹底比較!
最後にかんたんなクロス取引シミュレーターをつくってみました。
株の保有日数とは、取引をしてから品渡しをするまでの期間のことです。クロス取引は最低でも1日をまたぐため、最小の保有日数は2日となります。
また、このシミュレーターでは制度信用取引で発生する逆日歩は含まれませんので注意してください(取引は、逆日歩の発生しない一般信用取引がオススメです)。
株の保有日数
- 2日
- 3日
- 4日
- 5日
- 10日
約定代金(以下)
- 10万円
- 20万円
- 30万円
- 40万円
- 50万円
- 100万円
| 証券会社名 | 現物買い 手数料 |
信用売り 手数料 |
貸株料率 | 貸株料 | 総合コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI証券 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 円 | 円 | ||||
| GMOクリック証券 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 円 | 円 | ||||
| SMBC日興証券 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 松井証券 | 円 ※ボックスレート |
円 | 円 | ||
| 三菱UFJ eスマート証券 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| マネックス証券 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 円 | 円 | ||||
※表内の料金は税込です。
※ネット注文手数料です(電話注文は別手数料)。
※SBI証券の手数料は「ゼロ革命対象者」の場合です。
※松井証券の手数料は現物買い・信用売りの両方をおこなった場合の費用になっています。





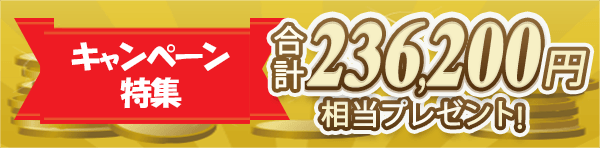
この場合の貸株料は、たとえば10日間保有していたら27円という費用感です。あまりに長い期間でなければ、そこまで気にしなくてもよいコストですね。