- TOPページ
- 株主優待の裏ワザ・お得情報
- 【クロス取引で損をする?】配当金と配当落調整金の違い・しくみをわかりやすく解説!
【クロス取引で損をする?】配当金と配当落調整金の違い・しくみをわかりやすく解説!
株主優待を低リスクで取得できる方法に「クロス取引」がありますが、それに関わる配当関連の制度・しくみは混乱しがちです。
具体的には「配当」・「配当落調整金 」・「配当落調整額」といったものがあるのですが、名前が似ていて違いがわかりにくいですよね。
しかし、この違いをしっかり理解せずにクロス取引を進めてしまうと思わぬ損をしてしまうかもしれません。
【クロス取引をする人へ】一旦これだけ覚えておきましょう!
これからご説明することは、税制も関わり非常にややこしくなってきます。取り急ぎ覚えておきたいことは、下記に該当したときに損をするケースがあるということです。
損の可能性があるケース
- 一般信用取引でクロス取引をする
- 配当が高い
一旦こちらを覚えておいて、当てはまりそうだと感じたときに下記を熟読してみてください!
配当とは
さて、まずは配当のおさらいです。配当は「企業が物を売ったりして稼いだお金の一部を、私たち株主へ支払うもの」です。
株主はその企業の持ち主なので、その企業が儲けたお金の中から配当をもらう権利があるのです。
1株の配当が10円の場合、100株を持っていれば「10円×100株=1,000円(税引前)」の配当がもらえることになります。
配当落調整金(配当落調整額)とは
一方の配当落調整金は、配当の補填という意味合いで存在する「信用取引の売建てのみで発生する支払いの仕組み」です。
実は買建ても無関係ではないのですが、一旦売建ての立場で説明しますね!
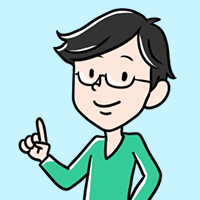 ひっきー
ひっきー
さて、配当落調整金の具体的な発生タイミングは、空売りした銘柄(売建玉)を配当権利確定日を超えて持ち続けた場合に発生します。
空売りをする人は、ほかの投資家や証券会社(以下、貸し手)が保有している株を借りて市場で売りますが、そのまま配当権利確定日をまたいでしまうと、貸し手は本来受け取れるはずの配当を受け取れなくなってしまいます。
そこで、その「貸し手が受け取れなくなった配当を補うため」に、空売りした人が配当相当額の配当落調整金を貸し手側に支払うルールになっているのです。
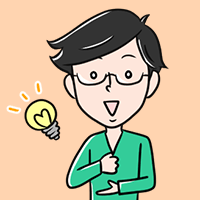 ひっきー
ひっきー
これが冒頭でお伝えした「配当の補填」です。
またその逆に、信用取引の買建てをして配当権利確定日をまたいだ場合には、配当落調整金を受け取ることができます。
「配当落調整金」と「配当落調整額」という言葉について
なお「配当落調整金」と「配当落調整額」という言葉がありますが、これは証券会社によって表記が異なるだけで意味は変わりません。
また、配当落調整金の支払い・受け取りが確定するタイミングは、通常の配当と同じです。
配当と配当落調整金の違い
ここまでで配当と配当落調整金の概要を解説しましたが、さらに踏み込んで重要な違いを説明します!それは「所得区分」と「税制」です。
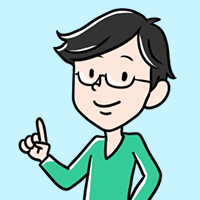 ひっきー
ひっきー
所得区分と税制の違い
配当の所得区分は「配当所得」となり、20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)が源泉徴収されます。
一方の配当落調整金の所得区分は「譲渡所得」とされ、制度信用取引の場合は15.315%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収され、残りの住民税5%は確定申告や年末調整で精算されます。
また、一般信用取引の場合は源泉徴収されず、譲渡所得として確定申告で合計20.315%相当(所得税+復興特別所得税+住民税)を精算します。
 ひっきー
ひっきー
ちょっとむずかしいですよね。ですが、売建て・買建てのどちらの立場も把握するとわかりやすくなります。
【売建ての場合】支払い金額の違い
制度信用取引の売建てで発生した配当落調整金を支払う場合、源泉徴収分(15.315%)を差し引いた金額である「配当 × 84.685%」を支払います。
一方の一般信用取引の売建てで発生した配当落調整金を支払う場合、源泉徴収はされないので「配当の100%」を支払います。
このため、一般信用の方が配当落調整金の支払額は多くなることを覚えておいてください。
【買建ての場合】受取金額の違い
さて買建て側からみると、制度信用取引より一般信用取引の配当落調整金の方が受取額が多く、一見得をしているようにみえます。しかし、これは税の納付タイミングの違いによる錯覚です。
制度信用取引の買建てでは、配当落調整金の受取時に「15.315%が差し引かれた金額」を受け取り、その後で住民税である5%を納税します(合計20.315%)。
一方の一般信用取引の買建てでは、配当落調整金の受取時に「源泉徴収なしの金額」を受け取り、後で20.315%を納税します。
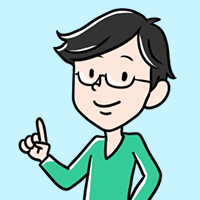 ひっきー
ひっきー
つまり結果として、制度信用取引・一般信用取引のいずれの場合も、買建て側が受け取る配当落調整金の最終的な手取りは「本質的に同じ」といえるのです。
クロス取引で損をしてしまうケースがある?
買建ての場合は、とくに気にしなくてもよいということがわかりました。しかし問題は売建て側です。売建てといえば…クロス取引ですよね。
クロス取引では「現物株」と「それと同数の売建玉」を持つことになります。ということは優待クロス取引をする場合、配当落調整金の支払金額が密接に関わってくるのです。
一度、現物株でもらえる配当金と、売建てで支払わなければならない配当落調整金を整理してみましょう(配当額が50円と仮定します)。
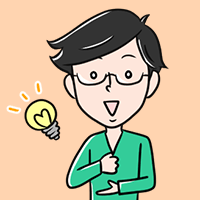 ひっきー
ひっきー
| 項目 | 計算式 | 受取/支払額 |
|---|---|---|
| 現物株で受け取る配当額 | 50×(1 - 0.20315) | 39.84円/株(受取り) |
| 制度信用取引 配当落調整金額 |
50×(1 - 0.15315) | 42.34円/株(支払い) |
| 一般信用取引 配当落調整金額 |
50×1 | 50円/株(支払い) |
優待を低リスクで取得できるクロス取引ですが、実は損をしてしまう場合があります。それは「配当が多い場合」です。
上記のとおり、制度信用取引の配当落調整金は気にするほどの差は出てきませんが、100%を支払う一般信用取引の場合は損をしてしまうケースが割と出てくるのです。
上記の条件に「100株でもらえる優待価額=1,000円」という条件を設けて、具体的な例をだしてみます(わかりやすくするために手数料・金利は無視します)。
制度信用クロス取引の場合
| 現物株で受け取る配当額 | 39.84円/株(受取り) |
|---|---|
| 制度信用取引 配当落調整金額 |
42.34円/株(支払い) |
| 差し引き | -2.5円/株 |
100株をクロス取引すると-250円の持ち出し。優待価額は1,000円あるので、トータル損益 = 1,000円 − 250円 = +750円
一般信用クロス取引の場合
| 現物株で受け取る配当額 | 39.84円/株(受取り) |
|---|---|
| 一般信用取引 配当落調整金額 |
50円/株(支払い) |
| 差し引き | -10.16円/株 |
100株をクロス取引すると-1,016円の持ち出し。優待価額は1,000円あるので、トータル損益 = 1,000円 − 1,016円 = -16円
まとめ
具体的な例をまとめると次のようになります。
| 信用区分 | 100株コスト | 優待価額の損益分岐点 |
|---|---|---|
| 制度信用 | −250円 | 250円未満で損 |
| 一般信用 | −1,016円 | 1,016円未満で損 |
このように「配当額が高い場合」や「何百株もクロスをする場合」、また「配当と比較して優待価額が極端に低い場合」などにこのようなケースが起こってきます。
 ひっきー
ひっきー
ちなみに配当金額は株数に比例しますが、優待価額は株数に完全に比例しないこともあります。また、各手数料・金利も考慮しないといけません。優待クロス取引は低リスクで優待がもらえる代わりにこういった点には注意ですね。
ところで制度信用取引での売建てはクロス取引の損益分岐点が低いからいいじゃん!と思われた人は要注意です。制度信用取引では「逆日歩」がつくおそれがあり、さらに高額なコストを支払う可能性もあるのでおすすめしません。
今回ご紹介したとおり、優待クロス取引を一般信用でおこなうと損になる可能性はあるものの、配当金額に注意さえしておけばクリアできる問題なので、取引は一般信用取引をおすすめします!





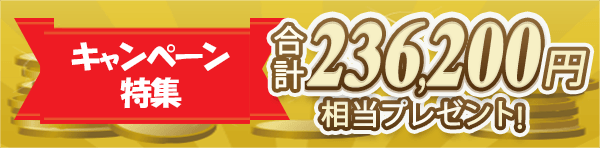
このページでは、これらの違いやしくみ、損をする場合のシミュレーションなどを詳しく説明していきます。